妻が本棚が欲しいという
我が家は私も妻も文系研究者ということで、自宅は本で溢れています。子供がいれば、あるいは親と同居ということであれば、家族のためのスペースを設けて、こっちはある程度自重しようとなるのでしょうが、子なし二人暮らしだと誰にも遠慮などいりません。京都時代から私たちは古本屋の倉庫のようなところで暮らしてきました。
昨年夏に大阪市に引っ越し、それを機にもう少し本の収納方法を見直そうと、何度か話し合いを重ねてきました。リビングに置いていた文庫本は、広くてスペースがある廊下に、奥行きの浅い本棚を置いて収納してはどうかと妻が提案しました。妻は、壁一面の本棚がいいといいます。壁一面本棚というと、昨年妻の部屋に設置したイキクッカや、私の部屋に置いているパイン材組み立て本棚などがあります。

パイン無垢材薄型本棚は、組み立て済みの棚をいくつも組み合わせて積み上げることができます。今年の初めに、私の部屋の入り口に、高さ255cmくらいの本棚を作りました(天井高は265cmです)。これは非常に仕上げがよく、頑丈ですばらしいのですが、なにせ単価が高く、また送料もかなりかかりました。
自分で作るっていうのはどうだろうか
いい本棚をネットで調べる内、自作している人もいるのでは、と思って作例を調べました。2x4材や2x6材を柱として、バネや金具で天井に固定し、柱の間に棚板をつけるという工法が簡単で、色々な人が作例をあげているのが見つかりました。

2x材、天井固定器具、棚板と非常にシンプルな作りの本棚を見ていたら、これなら問題なく作れそうだと思いました。
父の霊に動かされて一気に作業が進む
ところで昨年秋に亡くなった父は、リフォーム職人でした。会社勤めだった父は、趣味であれこれ道具を揃えてDIY活動に励み、いつのまにか会社をやめ、リフォームが仕事になっていました。そんな父のもとで私も丸ノコやディスクグラインダーなど各種工具を一通り使えるようにはなっていました。
父の遺品でもあるスケールを使って、壁や天井の寸法を測り、iPadのノートに書き写して、設計図を作り始めたあたりで、なんとなくスイッチが入った感じがしました。
 iPadに書いた図面の一部。計算を間違えたりしても消して上書きするなど自由自在です。
iPadに書いた図面の一部。計算を間違えたりしても消して上書きするなど自由自在です。
まずは廊下に高さ220cm、幅192cmの造り付け本棚を作ることになりました。2x4材が安く加工しやすそうなので、ネットで注文しました。
ウッドデッキ用に面取りなどの加工ができた質の高い木材が買えます。ここで柱になる2x6材(奥行き14cm)と棚板になる1x6材(幅90cm)を注文しました。
柱や棚板の固定には、ネジで天井に固定するラブリコアイアンとディアウォールを使いました。

平安伸銅工業 LABRICO DIY収納パーツ 2×4アジャスター アイアン 屋外使用可 ホワイト IXO-1
- 出版社/メーカー: 平安伸銅工業
- メディア: Tools & Hardware
- この商品を含むブログを見る
2x4に限らず2x材ならさまざまな大きさの板を固定できます。

若井産業 WAKAI 壁面突っ張りシステム ディアウォール専用棚受け 左右1セット ホワイト DWT75W
- 出版社/メーカー: 若井産業(Wakaisangyo)
- メディア: Tools & Hardware
- この商品を含むブログを見る
本棚を組み立てる
部品が全て揃ったら、あとは組み立てるだけです。
1)すべての棚板の両端に、ディアウォール棚受けを取り付ける。
2)柱を立て、レーザー墨出し器、水準器でまっすぐな位置に固定する。
3)柱の上下両端に、一番下と一番上にあたる棚板を固定する。
4)上から順に棚板をネジで固定する。
上記のような手順で作業を進めました。





設計図通りにドリルドライバーでネジを打ち込む単純作業ですが、棚板は22枚もあるので、だんだん疲れてきます。しかし汗だくになりながらも、父だったらこんな作業は一気に終えてたはずだなと思うと、作業を中断する気はなくなりました。結局日曜日のお昼の時間でだいたい作業が完了しました。
自室の入り口にも本棚を増やしたい
廊下の本棚を作る前から、せっかくだし、自分の部屋にも本棚を増やしたいという気になっていました。

廊下の本棚のほうは、木材をネットで注文したのですが、どうしても大きいので送料が高いし、配送の際にも玄関まで降りて受け取らないといけないし、梱包材などゴミが大量に出ることもあります。2x材なら大きいホームセンターでも売ってるはずです。そう思って今度は自分の車で西九条のホームセンターまで買いに行ってみました。
天井までの高さが265cmあるので、柱になる2x材は天井金具の分を除いて257,5cmにカットしてもらいました。本当に車で運べるか最後まで不安でしたが、後部座席をトランクスルーにして、木材の端がシフトレバーに接触するくらいギリギリの寸法でした。
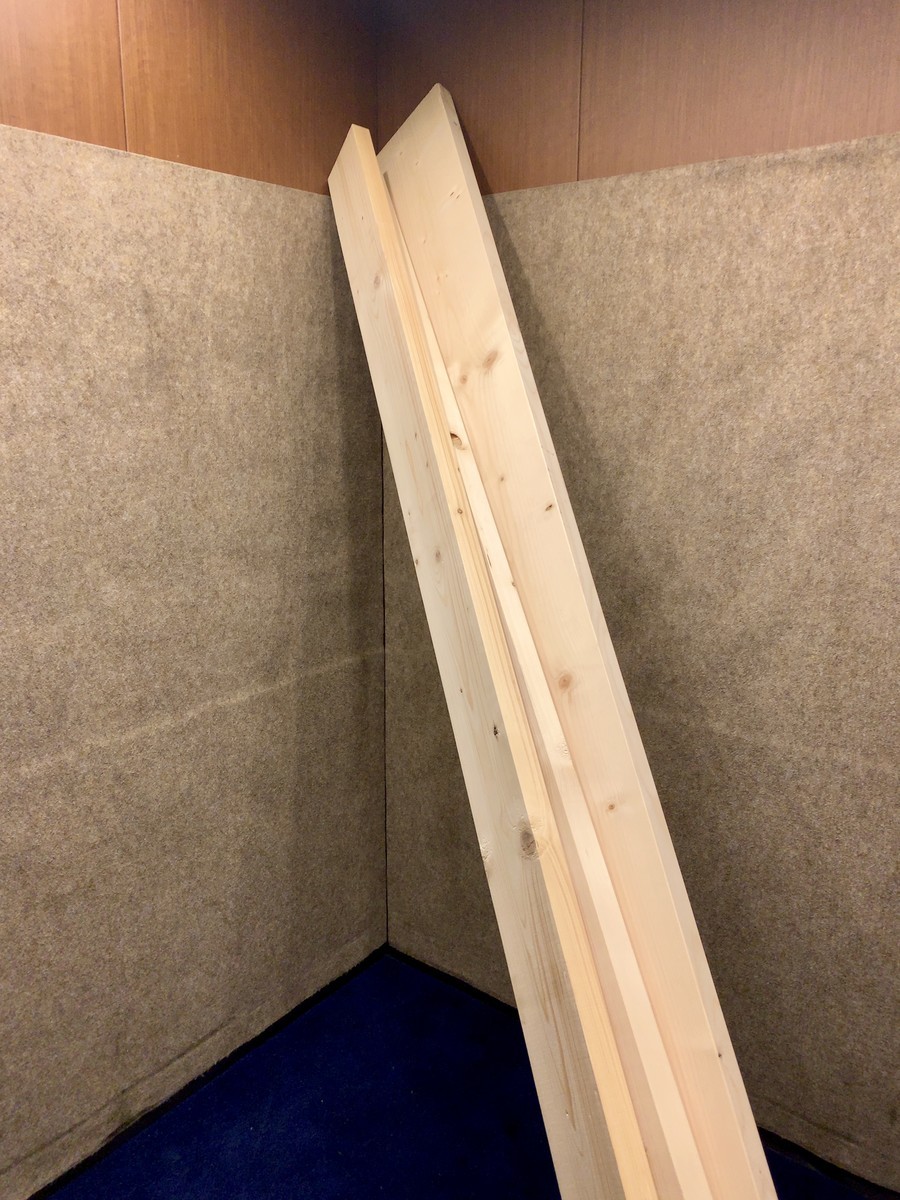

木材の研磨と塗装
今回はホームセンターで買った材木ということもあり、処理が不十分で、ささくれなどが目立ちました。どうせならきれいに仕上げたいので、やすりがけとオイルステインによる塗装もすることにしました。


オービタルサンダー は、紙やすりをバネで固定し、電動でヤスリがけをする道具です。どんどん木材がなめらかになるので非常に気持ちがいいです。



木材の加工と組み立て
塗料が乾いたら、金具や棚受けなどを取り付け、本棚を組み立てます。

今回は前回よりも棚板の数がずっと少ないので、はじめに柱の方に棚受けをつけた状態で、柱を立て、棚板を固定していきました。

これが父が大切にしてきたレーザー墨出し器です。買った当初は20万円以上したといいますが、メルカリで売ろうと思ったらずっと安かったので、手元に残して使っています。

今回は部屋の入り口にL字に棚を立てるので、柱に合わせて木材を少しカットする必要がありました。父が昔くれたよく切れるノコギリを久しぶりに使いました。

左手の棚受けに載っている部分が、先ほどカットした箇所です。

このように、入り口の引き戸周辺のデッドスペースにちょうどいい本棚ができました。
もともと木工作は得意な方でしたが、ほんとうに今回は父の霊が乗り移ったように、夢中になって作業しているうちにどんどんできあがっていたような感じでした。初盆を前にして、父の霊魂も力を持て余しているのかもしれません。あるいは私がいつの間にか死んだ父の能力を自分のものにしていたのかもしれません。
何にせよ、ちょうど授業がなくなる期間で時間的余裕があるので、これからさらに少し本棚を作ったりしたいと思っています。